はじめに
会社でAIツール導入の話をすると「俺たちの仕事なくなるんじゃない?」というような話になることもあるかと思います。
今回はたまたま見つけたYouTubeの動画で、マイクロソフトで実際にAI開発してる現役エンジニアのインタビュー動画でした。「1.5万人レイオフの裏側」とか物騒なタイトルでしたが、中身は非常に勉強になる内容でした。
「AIでエンジニア不要論」の実態を、現場の人がどう見てるのか気になって見てみたら、これが想像と全然違った話だったので共有します。社内でAI活用を進める上で、本当に重要な視点を学べました。
YouTube動画の紹介
動画の主役は牛尾剛さん、マイクロソフトのAzure Functionsチームのシニアエンジニア。シアトル在住で『世界一流エンジニアの思考法』の著者でもある方です。
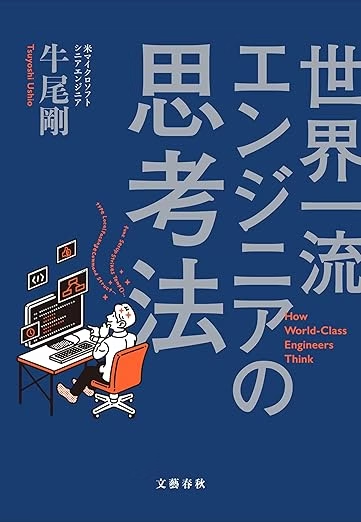
面白かったのが「ディープコードリーディング」という概念です。AIを使ってコードを100%理解することを目指すという話で、「1個目のPRを読むのに2日かかったけど、2個目は40秒」っていう具体例が印象的でした。
あと、みんなが気になるレイオフの話も出ていましたが、単純に「AIで人が不要になった」じゃなくて「GPU買うお金が必要だから」という現実的な理由。牛尾さんは「AIは無限に忍耐強い先生」「エンジニアはドライバー、AIは高性能エンジン」という比喩で説明していて、この辺りの生々しい話が、技術系YouTubeにありがちな夢物語じゃなくて良かったです。
実際に生成AIを利用している場面
動画を見て、牛尾さんの考えに非常に共感しました。というのも、私も日常の生成AI利用で、システム開発や構築よりも、過去システムに関連するドキュメントの理解に圧倒的に多く使っているからです。
具体的には、ネット上やCopilotで見つかった社内ドキュメントを「自分なりにほしい情報」として短時間で理解するためにAIを活用しています。レガシーシステムの仕様書や過去の障害報告書、ベンダー提案書などを「なぜこの構成になってるのか」「他の選択肢と比べてどうか」って聞きながら読み込むと、今まで「なんとなく良さそう」で済ませてた部分が、論理的に説明できるレベルまで理解できるように。
牛尾さんの「ディープコードリーディング」をドキュメント分析に応用している感覚で、まさに「100%理解を目指してAIを活用する」という考え方そのものでした。AIを単なるコード生成ツールではなく、理解を深めるためのツールとして使う発想が、実務にとても役立っています。
会社で展開していくなら…(現実的な話)
正直なところ、どんどんドキュメントの理解に活用していこう、と言ってもすぐ活用できるようにはならないでしょう。理由は以下です。
まずは温度差、そんなにAIに依存して大丈夫なの?という慎重な考えの方もまだまだいると思っています。そして製造業なら技術情報の漏洩は致命的だから、AIを使うのは怖いなどという人もいるんじゃないかと思います。
でも、段階的に試すなら価値はあると思います。少しでも感度高く学んでいる人は飛びつくような考え方だと思っています。そんな人たちに向けて実業務での利用イメージがわくような使い方を、講習やコンテンツとして発信していければなと考えています。
この動画で学んだ重要なのポイントは「AIに仕事を奪われる」ではなく「AIで理解力を底上げする」という意識転換を促すこと。牛尾さんの話は、この意識改革に非常に有効な材料だと感じました。
まとめ
結論として、「AIでエンジニア不要論」は今時点のAIのレベルではまだまだ起こりえないでしょう。でも「AIで仕事のやり方が変わる」のは間違いないです。
特に製造業の社内SEなら、レガシーシステムの理解や複雑な仕様書の分析で威力を発揮しそう。「無限に忍耐強い先生」って表現が的確で、分からないことを何度でも聞ける環境って、実は学習効率を劇的に上げてくれます。
この動画から学んだ最も重要な視点は、AIを「脅威」ではなく「理解力を高めるツール」として位置づけることでした。社内のAI活用を広める上で、技術論だけでなく、こうした本質的な考え方を共有することが鍵になりそうです。
ぜひ一度、この動画を視聴してみてください。AIに対する見方が変わるかもしれません。そして、みなさんの会社では、AI活用についてどんな話し合いがされてますか?
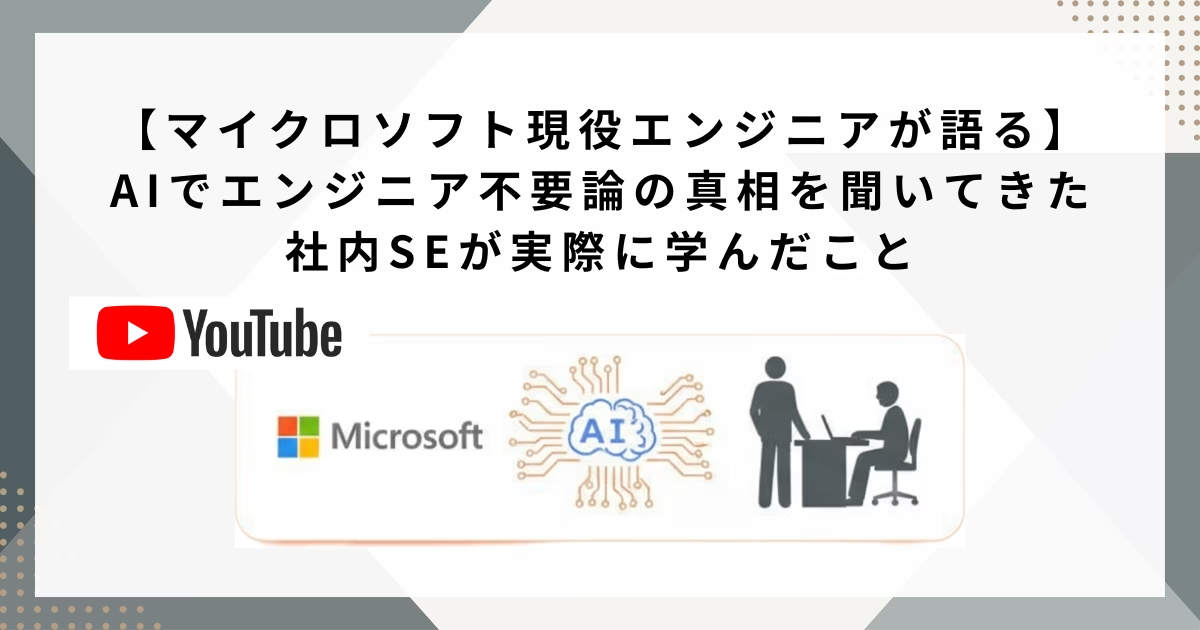
コメント